
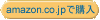
ぼくのプレミア・ライフ
(ニック・ホーンビィ/新潮文庫) |
●ニック・ホーンビィの「ぼくのプレミア・ライフ」(新潮文庫)はフットボール・ファン必読の書である。腰巻にこんな風にある。「アーセナルにとりつかれてミリオンセラー作家となった男の魂の記録」。これ見ると、あんまり買おうって気になれないっすよね。で、ずっと無視してたんだけど、実は最高におもしろいのだ。ワタシゃ、イングランドのプレミアリーグにはほとんどなじみがない。そのあたりが引っかかるかなと思ったのだがノープロブレム、セリエAな人だろうがJリーグな人だろうがブラジル萌えの人だろうが関係なし。
●ホーンビィは作家であり、他に訳書も出版されているが、この「ぼくのプレミア・ライフ」は基本的にスポーツ・エッセイ。アーセナルなんていう冴えないチーム(のようである、リーグでの位置付けは。最近は様相が異なるかもしれないが)にとりつかれた一人の男の個人史にすぎないものが、なぜこうもおもしろいのか。一つには万国共通のサポーター気質がもたらす共感ゆえ。非スポーツ・ファンから見ればバカバカしいにもほどがあるのかもしれないが、贔屓のチームの勝敗が自分の人生に決定的な影響を与えると信じ込んでしまうところなんて、まさにそう。仕事も人間関係もみーんなアーセナルによって成功するか失敗するか決まっちゃうみたいな運命論。バカでしょう。でもそれってある。
●ホーンビィはアーセナルの成績と人生の成功について比例関係を妄想しちゃってるんだけど、ワタシなんかはその逆も考えちゃう。つまり、こう。「おおお、ニッポン代表(あるいはマリノス)、こんなスゴい勝利を収めちゃったよ。フットボールの神様、ワタシはその代償としてなにかを捧げなければいけないのでしょうか」。いつもそうじゃないっすけどね。
●もう一つ、おもしろいのは外から見てても分からないイングランド・フットボール文化の懐の深さみたいなものに触れることができるってこと。浦和にも鹿島にもない、母国ゆえの染み付き具合。さらにイングランドならではのバカさも知ることができる。約40名の死者を出した「ヘイゼルの悲劇」について、よく言われる解釈とは違った真実が描かれてるのが興味深かった。その辺の話はまた改めて。(2000/08/25)
●先日、ここでご紹介したニック・ホーンビィ著「ぼくのプレミア・ライフ」(新潮文庫)、かなり反響あり。サッカーに魅了された少年がサッカーバカの大人になるまでの非・成長の物語(笑)。で、「ヘイゼルの悲劇」についてのイングランド人である著者の見方がおもしろかった。
●「ヘイゼルの悲劇」ってのは何か? 一般に伝えられる解釈はここにあるんだが、簡単に説明すると、スタジアムでイングランド人のフーリガンが暴れて、イタリア人39名が亡くなったという悲劇的な事件。舞台は中立地であるベルギーのヘイゼル・スタジアム。1985年のチャンピオンズカップで、リヴァプール(イングランド)とユヴェントス(イタリア)が対戦した。イギリスは不況の真っ只中。労働者たちは日頃の憂さを晴らすべく、フーリガンとなって大暴れ、イタリア人たちの席へなだれ込み、壁が倒れ、大勢の人が圧死した……。
●なんだけど、ホーンビィはそんな風には見ていないんだな。当時英語教師をしていた彼は、教え子のイタリア人たちと一緒にテレビでこの試合を観ていた。ウキウキした気分でテレビをつけたら、とんでもない事件が起きて、善良なイタリア人生徒たちに何が起きているかを説明してやらなければいけなかった。だから、事件に対してイングランド人として深く恥じ入り、怒りを感じている。フーリガンなんて連中への共感はわずかたりとも持っていない。しかし、イングランドに生まれたフットボール・ファンとして、その場で何が起きていたかってのは本能的に理解している。
●ホーンビィ曰く「イングランド人はただ走ったのだ」。イングランドの若いファンなら半数は面白半分にやったことのある行為。敵のサポーターを怖がらせてやろう、自分たちをマッチョに見せてやろう。そうやっておもしろがる、ただそれだけ。が、その単に「走る」という行為を、イタリアの中産階級の男女たちは真の脅威と受け取り、恐怖のために必死になって逃げた。「逮捕されたリヴァプール・ファンは心底とまどっていたに違いない。…まったくイングランド的な犯罪だった。彼らはただ、母国の文化を他の国へと移植してみせただけだった。だがその文化は理解されず、死者が出てしまった」
●「ヘイゼルの悲劇」がちょっとした文化の差異によって引き起こされたものだって解釈を、ワタシはこの本ではじめて知った。欧州間でもこうっすからね。「ったく、イングランドの悪ノリ文化ってのはどうしようもねえなあ」なんて他人事で済ませられないのが2002年のワタシら。お互いに分かんないのはしょうがないわけで、それを前提にした警備のあり方が必要になってくるってことか。再び悲劇が起きる余地は残されている。(2000/09/01)
|