
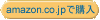
「モーツァルトはどう弾いたか」
(久元祐子/丸善ブックス)
|
●「モーツァルトはどう弾いたか」(久元祐子著/丸善ブックス)を読む。ピアニストとして活動する著者が、演奏家の視点からモーツァルトの人と音楽に迫る一冊。タイトルからも分かるように、焦点はピアニストとしてのモーツァルト、モーツァルト時代のピアノに当てられている。モーツァルトの手紙などの文献を頼りにその音楽活動を追いながらも、とりあげられる事例は具体的であり、モーツァルトのピアノ音楽を(特にピアノ・ソナタを)愛好する人にとっては示唆に富む内容。たとえば、「トルコ行進曲」のテンポはどう設定すればよいのか(ご存知のように、ピアニストによって1.5倍くらいは速度が違う)。幻想曲ニ短調の最後の数小節は本来未完であり他人の手が入った楽譜が一般に出版されているが、これはどうすればよいのか。時折左手のパートがすっぽり抜け落ちている戴冠式協奏曲を印刷譜通りに弾くことに意味はあるのか。
●この本の親切なところは一部ネットとの連動をはかっているところで、文字だけでの言及では伝わらないような事柄をウェブ上に音を置いて、耳で確かめられるようになっている。これは技術的にはシンプルなことであっても、非常に効果的で実際的なやり方。
●しかし、大変だよなあ、モーツァルトを弾くのは。ピリオド楽器派の隆盛のおかげで、今じゃワタシらはこの時代の音楽を弾くことの難しさについて、すっかり耳年増状態。まず、楽器そのものが大きく違う。さらに紙に固定された出版譜というもののありかたが違う。当時の奏者(しばしば作曲者本人)にとっては自明ゆえに楽譜に書かれていない情報がある。やれやれ。
●だから「モーツァルトはどう弾いたのか」、すごく知りたい。が、結局のところは分からない。しかし分からないが、演奏家は何らかの態度表明は迫られるわけで、評伝的なアプローチによったり記譜法を解釈しながら、形にしていく。その過程の一つをここに見出しながら紐解いていくのもいい。(2000/08/11) |